こんにちはgrandstreamです。
今回は、「はじめての哲学的思考」苫野一徳(とまのいっとく)について、気のままに書評を書いてみようと思う。
まず最初に、お伝えしたいのが、かなり読みやすいということだ。
哲学書って結構専門用語とか、難しい言い回しとかがたくさん出てきて「イマイチようわからん!」となりがち。
でもこの本は、きっと高校生でもそれなりにスラスラ読めてしまうだろう。予備知識もいらない。だから、哲学に興味があるけどどの本を読んでいいかわからないと思っている方に、最初に手にとってほしいと思う。
前置きはこのぐらいにして、中身に入っていこう。
本書のざっくり構成
さて、本書がどんな構成になっているか僕なりにまとめてみた。
- 哲学とはなにか?
- 哲学と宗教、哲学と科学との違い
- 哲学的思考の注意点
- 哲学的思考のやりかた
- 哲学対話について
ざっくりこんなところだろうか。テツガクって何なの?ってところからわかりやすく説明してくれている。
更には、「哲学的に物事を考える」とはどういうことか、についても、注意点を交えながら説明してくれており、実生活でも応用できるんじゃないかと思った。
本書の最後には、いわゆる「哲学対話」、つまり、複数人で、とあるテーマ(恋とはなんなのか?)について「あ〜それって本質だよね」って納得できるまで話し合う対話の例を載せてくれている。
個人的に印象に残ったところ
では、本書の本筋とズレてしまう可能性もあるが、個人的に印象深かった箇所をピックアップしてみようと思う。
実存的問題と社会的問題
いきなり難しい単語が出てきたが、とりわけ、僕は「実存的な問題」って何なのか、イマイチよくわかっていなかった。
でも、本書によれば、以下のような問題のことだ。
- なぜ学校に行かなきゃいけないの?
- どうすれば不幸から逃れられるか?
- 将来どう行きていけば良いのか?
わかりやすいですよね。人間の存在からくる悩みとでも言い換えても良いんじゃなかろうか。
あと、社会的問題。
- どうすれば貧困をなくせるか
- どうすればテロをなくせるか
まあ、これはわかりますよね。
哲学では、こういった難題に、立ち向かうための「考え方のコツ」を提供してくれると筆者は言っている。
哲学は、物事の本質をとらえる営み
世の中に絶対に正しいことはない。でも、みんなが、「あ〜それって本質的だよね」と納得しあえることがある。例えば、恋について、教育について。
絶対の真理じゃなくて、できるだけ多くの人が納得できる考え方(共通了解)にたどり着けるらしい。哲学を持ってすれば。
民主主義は哲学者が考えた
民主主義、という今では当たり前の考え方も、実は哲学者が「よい社会」とはなにかについて本質を考え抜いたことから始まったのだとか。いまから二百数十年前のことだ。
それまでは、人々はひたすら戦争を繰り返したり、強い権力者が弱者を強権的に支配するというスタイルだった。しかもこれが有史以来1万年以上も続いたのだ。
これはたしかに!と思った。日本国内でも数百年前までは、常に戦は耐えなかったし。
そもそも、なんで戦が起きるか、それは「自由への欲望」があるからだ、とある哲学者が本質を見抜いて見せたのだ。
であるならば、個人個人の自由をお互いに認め合えば良いんじゃないか?という考えに至ったんですね。これが民主主義の始まりだと。
一人の強者が自由を振りかざしちゃうと、それ以外の人たちは不自由になっちゃいますからね(で、また戦争が起きる)。
こうして、今現在僕らが享受している、比較的平和な、民主主義社会が生まれたというわけだ。。実に感慨深い…。哲学の威力を思い知らされる。
宗教は、信仰するものに「生きる意味を」与える
まあ、見出しのとおりだが、これは哲学と宗教の違いに関しての部分で出てきた話だ。
確かに、キリスト教であれば、神の教えに従って生きれば死後に救われるとか。確かに、生きる意味を与えてくれると言うのは実に心強いというか…。
いくら哲学や科学でもこれには太刀打ちできないというのはよく分かる(気がする)。
日本人であり、特別な信仰心を抱いているわけではない僕にはちょっと体感的には理解しづらいが…。信仰心が深い人がある意味、羨ましいとも思える。
科学にできること、哲学にできること
これに関して、いい例が載っていた。
「恋」に関して、科学は、恋をしている人の脳内からどんな化学物質が出ているかを明らかにすることはできる。
でも、僕たちにとって恋が何なのか、という意味の本質は、科学は教えてくれないよねっていう。
それを明らかにするのが哲学の仕事なのだと。
一般化のワナ
ここでは、哲学的思考をする上での注意点を筆者は述べている。
とくに、腑に落ちたのが「一般化のワナ」。どういうことかというと、人は自分の経験を過度に一般化して、それが絶対に正しいかのごとく考えがちだということ。
例えば、努力して努力して這い上がって、経済的に大成功をおさめた人がいるとする。するとこういう人は、貧しい人に向かって「それはね、あなたの努力が足りないんだよ」と啖呵を切ってしまいがちだということだ。
これはめちゃくちゃ納得だ。人は自分の経験に強く影響を受けてしまう。
人が貧しいのには、本人の努力ではどうしようもない運とか、環境要因なんていくらでもあるのに。
だから僕らがある事柄に意見を言うときは、過度に自分の経験を一般化していないだろうか?と一歩立ち止まってから発言するようにしたいところだ。
自分の信念をただ相手にぶつけるのではなく、「これは独りよがりな考えかもしれないんですが〇〇っていうことはアリえませんかね?」ぐらいのテンションで対話をすれば、話し相手との「共通了解可能性」が得られるかもしれない。
それが物事の本質に迫っていく第一歩になると感じる。
帰謬法(きびゅうほう)について
これは何かというと、「あなたのいっていることは絶対に正しいといえるの?それって絶対なの?ぜぇぇぇったいなの?」みたいな問いかけのことだ。
これはかなり強力で、どんな命題も否定できちゃうのだ。
たとえば「カラスは黒い」っていう命題があったとしても、証明しようがない。僕がみているカラスの色と、君が見ているカラスの色が同じだとどうやって証明すれば良いのか。更には、動物によっては、赤外線しか見えない動物もいるわけだし。
だから、帰謬法は相手を言い負かすのにはもってこいなんだが、相手との「共通了解可能性」を探って行く上では、建設的な議論はできないよねっていう。
帰謬法を乗り越える奥義
でも、先程の、帰謬法(とにかく疑いまくる)を乗り越える奥義がある。
それがかの有名な、デカルトの「我思う故に我あり」である。あらゆるものを疑ったとしても(帰謬法)、一切のものを疑っている「私」自身の存在は疑えないでは無いか!と。
でも、実のところ、この「私」だって疑えるらしい。つまり、昨日の私と今日の私が同じであるかなんてわからないよねっていう。数年単位で身体の細胞が全部入れ替わるって話もあるし。
んで、この問いを乗り越えたのが、フッサールという人らしい。
彼が言うには、今僕たちに何かがたしかに「見えちゃっている」という”現象”は疑えないではないか!と言ったわけだ。
これが、あらゆる思考の出発点となっていくわけですね。おもしろい。
僕たちの信念は欲望の別名
これはこうあるべきだと自分が思っている信念は実は欲望なのだと筆者は言う。僕が何かに対して抱いちゃってる欲望は疑えない。だから思考の出発点になりうる。
そこで、相手と対話するときは、お互いの信念(欲望)をさらけ出し、共通了解を探っていくことになる。
まとめ
さて、本書を読んでみて、気になったところについてまとめてみた。
特に、民主主義は哲学者が考え出した、というところで改めて哲学の威力を見せつけられた。
さらに、哲学的思考を深めていくに当たっての注意事項である「一般化のワナ」これも、うっかりやっちゃいがちなので気をつけたいところ。
それから、疑いまくること(帰謬法)から、思考の出発点である絶対に疑えないこと、すなわち、「見えちゃってる」「感じちゃってる」ということへ、長い歴史の中でたどり着いたこと。
そしてお互い、哲学的な議論を深めていく上で、その絶対に疑えない個人個人の信念(=欲望)を開示しあい、共通了解を探っていくことが重要だとよくわかった。
最後に、哲学入門としてこれほどわかりやすい本はそうそう無いと思うので、少しでも興味を持たれた方はお手に取ってみてほしい。
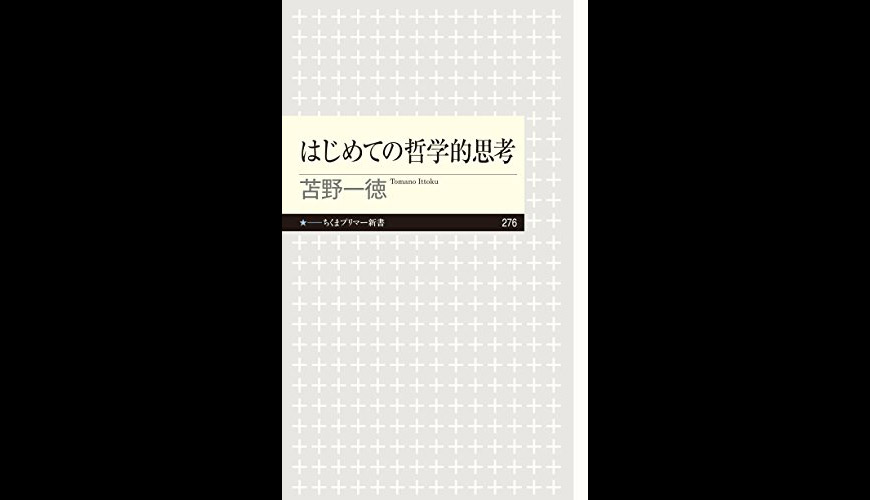
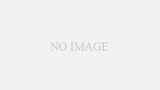
コメント